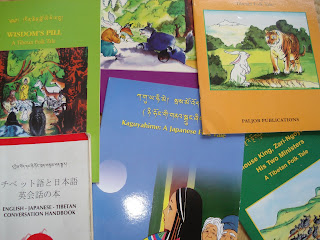中国の白書を拒否: 17か条協定 - 中国が何を公約し、何が果たされたのか、そして将来は?
東チベットのカムの都チャムドが中華人民共和国(PRC)に占領された後の1951年5月23日、チベットは、17か条の「チベットの平和的解放に関する協定」にサインすることを余儀なくされました。占領軍は、「協定へのサインか若しくは、チベットの他地域に対する即時的軍事作戦の展開か」の二者択一を迫りました。(写真) チベット亡命政権情報・国際関係省 チベット博物館
https://www.tibethouse.jp/news_release/2021/20210523_news.html
中国は、今月21日に、更に別に一つのチベットに関する白書「1951年以後のチベット:解放、開発そして繁栄」を発表しました。この白書において、「チベットの平和的解放70周年記念を機に、チベットの歴史と功績を再考し、新しい社会主義チベットの現在における真の全実態を披露するために白書を発表した。」としています。
白書にチベットは古代から中国の一部であり、17か条協定にサインすることによって、チベットは、海外の帝国主義者から解放されたと主張し、また、過去70年間におけるチベットの地域自治、民主主義、発展、宗教的そして文化的自由について公言しています。これは、国際社会を誤解させ、そして歴史的事実を曲解させる、更に別に一つの中国によるプロパガンダなのです。
2021年5月23日、チベットと中国の間で論争を巻き起こした17か条協定から70周年の節目を迎えます。中国は、チベットと祖国の統一を誇る声明を、大々的に発表することが予想されます。17か条協定の各内容について見直しを行い、中国に対しては協定を勝利したと捉えて祝うのではなく、チベット問題を解決に導くために協定について改めて考察するよう求めましょう。
17か条協定は、チベット独立の歴史の重要な転換点におけるチベット・中国関係の真実を明らかにする重要な根拠となる歴史的文書です。チベット政府は、中国共産党から協定へのサインを強要されましたが、その一方で、このことはチベットが協定以前において決して中国の一部ではなかったという事実を示す重要な証拠でもあります。
歴史的な視点から、1949年以前におけるどの時代においても、チベットが中国の一部であったことは一度もなかったという事実を明らかにしていくことは非常に重要です。確かにモンゴル、ネパール、中国そして英国の各国軍隊がチベットに入り、チベットの歴史上のある一定の期間、宗主権を行使しました。しかしながら、こうした国々の軍は、 使節として、侵略者として、あるいは、チベット政府の要請によってチベットに入り、その任務を全うすれば去っていきました。中国が、過去におけるこうした出来事を論拠として、歴史的にチベットが中国の一部であること主張することは根拠のないことなのです。仮に中国が、チベットを中国の一部であると主張するのであれば、他国も同様な主張を繰り広げることが可能であり、そうであるとするならばチベットは、中国をチベットの一部であると主張することができるはずなのです2。このような言い争いは起こるべくして起こるものであり、世界中のほぼすべての国々の政治史において見受けられるものです。
共産中国は、様々な実質のない根拠の下、チベットを中国の一部であると主張しようとしてきました。しかしながら、大半の作為的なプロパガンダと同様に、共産中国による主張の本質は変化し続けました。当初は、7世紀、チベットのソンツェン・ガンポ王(Tib:srong btsan sgam po)の時代に、唐の文成公主(皇帝の娘)がチベットの王女の一人となって以来、チベットは中国の一部であると主張していました。その後、中国の白書3において、14世紀にモンゴルの元王朝からチベットを継承し、後に、明と清朝からチベットを継承したと主張したのです。しかしながら、史実をゆがめることを目的とした、こうした欺瞞的で虚構とも言える主張は、中国の学者らによってさえ強く反駁されたのです。4
実のところ、チベットを占領して60年が経過した後でさえ、中国はチベット人を完全に打ち負かすことはできていないのです。歴史的な主張とプロパガンダにより、チベットの占領を正当化できなかった中国は今、地域の発展と「封建的農奴制からの解放」をもたらしたと繰り返し主張し始めました。
多くの人々は、中国との17か条協定が、チベット独立の終焉を意味すると信じています。しかしながら、実のところ17か条協定こそが、チベットが独立国家であり続けていたことを証明する重要な文書なのです。また、この協定は、中国がチベット問題の打開策として、チベットの「一国二制度」に合意したという事実の証明でもあります。しかし、この協定の本質とその成果は、中国共産主義の帝国主義的色彩を鮮明にしているとも言えます。本協定は、脅迫の下でサインされたものでしたが、ダライ・ラマ法王とチベット政府は、中国の要求に対処するために最善を尽くしました。一方、中国は、チベットの領地が完全に中国人民解放軍(PLA)の支配下にあると確信したとき、協定に違反し始めたのです。これこそ共産主義政権下にある中国の手法なのです。香港や台湾はこうしたチベットの経験から学び、中国による交渉の申し入れに対して警戒すべきです。5
中国は、チベットに対して最初に17か条協定の内容を提案し、後に、協定の内容を強要しました。チベットは、最初は協定に対して異議を唱えましたが、後に受け入れようとしたところ、中国は自らが強要した協定に違反するようになったことから、チベット人は抵抗し、再び協定に対して抗議したのです。しかしながら、中国は、協定を勝ち得たものと捉えて祝賀しており、この辺りに協定の皮肉があるのです!
さて、ダライ・ラマ法王とチベット亡命政権は、中国・チベット問題の解決を図るために、1987年に「チベットに関する5項目和平プラン」、1988年に「ストラスブール提案」そして、2008年に「真の自治に関する草案」という形で解決策を提案しています。これら3つの提案は、チベット問題の解決を図るという、チベットによるアプローチの3本柱とみなすことができます。また、この3つの柱は、17か条協定6、鄧小平主席の声明7、中国憲法8及び中国による3つの核心的利益と多くの共通要素を共有しています。
脅迫下であったとは言え、チベット政府が17か条協定にサインしたことは、中国が待ち望んでいた、チベットを中国の一部に組み入れるための口実を与えることとなりました。ダライ・ラマ法王は、1959年4月、インドのテズプルにおいて公式に協定について異議を唱えたところ9、国際社会が協定に関して真実を知ることとなり、中国はチベットを
占領する正当性を失ったのです。従って、国際法の観点からも、中国がチベットを占領したことは違法です10。中国は、台頭する超大国として、そして重要な国連加盟国として、チベットの権利に対する道徳的、国際的な正当性を得るため、この歴史的な失態を是正する必要があります。中国は、脅迫や残忍な占領を通じて、17か条協定に記されたすべての事項を成し遂げました。チベット問題の解決に向けて真剣に取り組んでいるのであれば、チベットに与えると合意しながらも、中国が、決して履行しなかった内容を誠実に思案する必要があります。
協定第3条:「チベット人民は、中央人民政府の統一された指導の下、民族地域自治を実施する権利を有する。」
協定第4条:「中央当局は、現行のチベット政治制度に変更を加えない。中央当局はまた、ダライ・ラマの確立された地位、職権、権力にも変更を加えない。各級官吏は、これまでどおりの職に就く。」
協定第7条:「チベット人民の宗教的信仰、民族風習及び習慣を保護すると共に、僧院は保護する。」
協定第11条:「チベット地方政府は、自ら進んで改革を進め、人民が改革を求めた場合、チベットの指導者との協議により解決する。」
中国がチベットに約束したこれらの4項目は、いまだ履行されていないばかりか、中国は協定に違反しているのです。
2008年に中国の指導者らに対して提案がなされた「真の自治に関する草案」は、このような歴史的文脈を考慮して研究されるべきです。この草案が、中国の3つの核心的利益からどの程度逸脱しているのか。さらに重要なことは、草案が、中国憲法の範囲内に含まれるのか、あるいはどの程度逸脱しているのかという視点で研究されるべきです。こうした研究は、チベットと中国が相互に受け入れ可能な合意に達するための協議を進捗させ、交渉のための共通基盤となるものです。
共産中国にとって大変残念なことに、1951年の17か条協定は、中国による侵略以前において、チベットが独立国家であったことを証明する重要な文書であり続けています。しかしながら、チベット人民は、現中国からの分離を模索しているわけではなく、ダライ・ラマ法王やチベット亡命政権による中道のアプローチに基づいて、この協定が問題解決のための共通基盤を見出すのに重要な役割を果たすことも可能なのです。また、チベット及び中国の3つの核心的利益は、チベット問題の解
決策を見出すことができる、合意可能な条件範囲(ZOPA)となり得るものです。中国指導部による、合意可能な条件範囲(ZOPA)の領域を思案する強い意志と誠実な努力は、17か条協定を通じて目論まれた道義に反する勝利を繰り返し訴えるより、はるかに相互にとって有益でしょう。
5月23日は、中国指導部が、チベット人民に対して何を約束し、何が真に果たされたのか、さらに、チベット問題の解決を図るための共通基盤を見出すためにどのように役立つのかを顧みて見つめなおす日であるべきなのです。
国際的情勢において、この協定こそ中国が約定をどのように見ているかを示す生きた証拠と言えます。
1954年、中国は、インドとの間に「パンシール協定(平和5原則)」にサインし、平和的共存と相互不侵略について合意しましたが、1962年に中国は、インドを攻撃しました。わずか数年前となる2017年に中国は、ドクラム事件を通じて、インドとブータンの領土に侵入しました。また、昨年中国は、インド領であるラダクに対する違法な侵略を行っています。
中国と英国政府は、1984年に共同宣言を出し、1997年の中国への主権移譲後、香港の高度な自治について合意したのです。共同宣言の第3条には、香港が保有するはずの特権について詳述されています。しかしながら、昨年、香港で何が起こったのかは皆さんご承知のとおりですし、香港の現状はどうでしょうか。
17か条協定は、ちょうど70年前にチベットで起こったことです。昨日のチベットは、今日の香港であり、チベットや香港をこのまま問題にすることなく成り行きに任せておけば、まもなく台湾、フィリピンそして尖閣諸島なども同じ道をたどることになるでしょう!
(翻訳:仁恕)
_____________
T.G.Arya, https://tibet.net/2019/03/tibet-has-never-been-a-part-of-china-anywhere-in-its-pre-1949-history/
In 763 AD, the Tibetan army of King KhrisrongDeutsan captured the Chinese
capital Ch’ang-an, the Chinese Emperor fled with his family and a large
following. TseponShakabpa, Tibet – A political history, p-39
3White paper 1992: Tibet – its
ownership and human rights situationhttp://www.china-un.org/eng/gyzg/xizang/t418894.htm
(1) Prof Hon Shing Lau, The Political Status of Tibet during Ming
Dynasty: An analysis of some historical evidence, City University of Hong Kong,
(2)Chinese Voices for Tibet, DIIR,( a) Cao Changqing, Independence – the right
of Tibetan people, p-80; (b) Chen Pokong, Has Tibet belong to China since
ancient times?, p-164; (c) Zhu Rui, Tibet has not been a part of
China since ancient times, p-193
5Tang Huiyun, “Why are people in Hong
Kong are concerned about the Tibetan problem?”, p-61, Chinese Voices for
Tibet, DIIR
The point 3rd, 4th, 7th and 11th of
the Agreement
7 “Everything is negotiable except
the independence of Tibet” – Deng Xiaoping
Article-4, “Regional autonomy is
practiced in areas where people of minority nationalities live in compact
communities…….” and Article-2,4 and 11 of Law of the PRC on Regional National
Autonomy
9Facts about the 17-point agreement
between Tibet and China, p-137, DIIR, 2001
10The Legal Status of Tibet – Three
Studies by Leading Jurists, p-93, DIIR, 1989
+012.jpg)